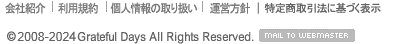|
ウェイネルのMILU日記 |
 |
|
| タイトル |
 |
昭和初期のカメラ事情 |

|
 |
おすすめ(19) |
 |
2024-06-19 01:17:13 |
|
|
確かに戦前は個人でカメラ(当時は写真機と呼んでいました)を持っている人はきわめてまれで、そのため写真は写真館へ行って撮ってもらうのが一般的でした。しかし昭和初期からは次第に国産のカメラも出回りはじめ、写真コンクールなども行われ、次第に一般の家庭にも普及し始めます。昭和10年頃には一般庶民に普及していったと考えてよいでしょう。当時のフィルムはロールフィムと云うフィルムを紙と一緒に巻き込んだもので、サイズはセミ判(6×4.5)や6×6判が主流です。35ミリフィルムを使ったライカ、コンタックス、などはやはり高嶺の花で庶民は手が届きませんでした。
カメラよりさぁ
フイルムが高かったのよ
現像料とかさぁ
昔は高かったんだぜぇ
昔のフイルムはもたなかったしねぇ
綿と樟脳を使ってフイルム作るんだけどさ
薬剤が揮発してすぐ使い物にならなくなるのさね
今より使用期限が短かったしねぇ
しかも良く燃えるんだわこれが
自然発火してさぁ
昔はテレビ局の地下の倉庫が火災起こしてたねぇ
映画会社の倉庫もね
そういうもんでさ
一般家庭で使うもんじゃなかったんだよねぇ
専門知識が必要なもんだったからさ
一般の人が買う理由もなかったのさね一般家庭に「写真機」があるようになったのは、戦後復興がかなり進んだ頃からです。
戦争前などでは、素人で「写真機」を持っているのはかなりのお金持ちの新しい物好きの人だけです。
日本のカメラ産業はまだ始まったばかりで、ドイツはもちろんアメリカの足元にも及びませんでしたし、日本人の所得も欧米に比べ格段に低かったのです。
輸入品のドイツで言えば中級のカメラでさえ公務員の初任給で一年分とかですから手が出なくて当たり前だったのです。つまり、今の給料で計算すると百数十万のぜいたく品です。
戦後も飢え死にしないのがやっとの時代にはカメラなど買う余裕はありませんね。
戦後すぐから町工場で作られたカメラも殆どは米兵のお土産と輸出用だったのです。
まあまあ、何とかカメラに普通のサラリーマンが手を出せるようになったのは二眼レフのリコーフレックスのレンズが歯車のが安く出始めた頃からです。
それでも、初任給では買えなかったのです。
昭和30年ごろになってやっと観光地でカメラを持った人を見かけるようになったものです。
そして、後は日本人の所得が伸びるに連れて、加速度が付いたように増えて行きましたね。
昭和40年代の後半になると、『メガネを掛けてカメラを肩に掛けているのは日本人』と言われるまでになったわけです。本格的な普及は昭和40年頃以降です。
しかし、一眼レフともなるとペンタックスSVやミノルタSR1、SR7でさえ初任給の倍位いでした。
ニコンFやライカは庶民にはなかなか買えない価格でした。
ある程度裕福な家庭ではキヤノネットなどを持っていました。フィルム代も高くて正月に入れたフィルムを1年かけてやっと1本を消化していました。
昭和30年後半には、フィルム代を節約するためにハーフ判のカメラが販売されました。
明治、大正に拘わらず、ごく平凡な写真でも当時の風俗・風景などがわかり貴重なものです。
絵画もそれなりに時代性を汲み取れますが、写真のほうがより身近で時の経過、真実味があります。一億総中流と言われ、テレビや車が一般庶民に浸透した1960年(昭和35年)ごろからだと思います。
第二次世界大戦前は「カメラ一台家一軒」と言われていた時代です。1930年当時トップメーカーであったドイツのライカというカメラは大卒サラリーマンの初任給が70円の時代に420円で売られていたそうです。大正のころとなるとお金持ちであっても余程の好事家以外はカメラなんて持っていませんでした。フィルムの感度が低くて撮影にも技術がいりますし、現在のフィルムのように簡単に扱えるものではなかったので、まず写真館にしかカメラはなかったのです。日本限定だと、二次大戦までは写真機は金持ちの持ち物、写真はなにかの記念日に写真屋さんで撮影してもらうもの、でした。
1950年にリコーフレックス3が非常に安価(といっても一般サラリーマンの月給の半分ちょっとなので、今で言うと10-20万くらいの感覚?)で販売され、大人気で売れたあたりが普及のきっかけでしょうか。
欧米だと事情がちょっと変わるようで、コダックのブローニーNo.2が1901年に出たときに、すでに「簡単に撮れて現像はコダックまかせ(カメラに猟奇を添えて返送すると、現像して新たなフィルムを詰めて返してくれる)が売りでしたから、遅くても戦前には一般家庭に普及していたのではないでしょうか。一般家庭で写真を撮るようになったのは、おそらくですが戦後昭和20年代辺りからではないでしょうか。
ただ、当時の一眼レフ機などはそれこそ給料の何ヶ月分かをつぎ込んでようやく買える、という水準だったようです。
Pentax SPという大衆機が1964年頃に発売されましたが、当時の価格が8000円、ほぼ同時期に発売されたOlympus PEN Fというカメラが26,500円だったそうです。
当時の大卒初任給がだいたい18,000円ほどでしたので、現在の価値でいうとほぼゼロが1つ多くつくような具合じゃないでしょうか。
経済成長期でもあった当時の大衆機ですら、現在の価値で8万円くらいと考えると、昭和30~40年代はまだカメラは贅沢品で、一般家庭に普及するという段階ではなかったのではないか、と推測します。
1970年代、昭和50年代になると、コンパクトカメラなどが数多く発売され、また当時の給与水準もかなり上がってきたという点と、円ドルの固定相場制が廃止されたことで海外からのカメラの輸入がしやすくなったようです。
この辺の事情を勘案すると、1970年頃に一眼レフの大衆機(Pentax SPやOlympus OM10など)ユーザーが増え、コンパクトカメラの選択肢も増えてきた、といったところでしょうか。
決定的な出来事は1986年(昭和61年)の「写ルンです」発売でしょう。
おそらく写ルンですの登場で、一般家庭で写真を撮る際の「お父さんがカメラを持つ」から「家族みんなで撮る」というスタイルに遷移したのではないかと考えます。
これらのことから考えて、いわゆる富裕層から一般糧に当たり前にカメラが有り、いわゆる「ハレの日」だけでなく、小さい子供の何気ない日常を写真に残すようになったのは1970年代くらいから、昭和40年代半ばくらいからなのでは、と思います。
|
|
|
|
|
| コメント(8) |
| oldlonlywolf |
2024-06-19 04:49:18 |
|
|
| デジカメが登場してから、フィルムという概念が無くなりましたね(^^) |
|
|
|
| NORITA |
2024-06-19 08:51:09 |
|
|
| ( ゚д゚)ウム素晴らしいですね(^^♪メンテ明け後もよろしくお願いいたします |
|
|
|
| fukurou5 |
2024-06-19 09:55:44 |
|
|
| メンテ明けもよろしくお願いします! |
|
|
|
|
2024-06-19 14:05:16 |
|
|
| メンテ明けよろしくお願いします^^ |
|
|
|
| 綿津見神 |
2024-06-19 15:28:40 |
|
|
| メンテ明けもよろしくお願いします^^v |
|
|
|
| めぐ02 |
2024-06-19 22:34:10 |
|
|
| なるほどφ(..)メモメモ |
|
|
|
| ちい吉 |
2024-06-20 12:27:48 |
|
|
| (*゚.゚)ホ・(*゚。゚)ホーーッ!! |
|
|
|
| パンダの庭 |
2024-06-20 22:49:03 |
|
|
こんな歴史があったんですね。興味深く拝見しました。
そういえば実家の倉庫にハーフ判のカメラっていうのがあった気がします。どういう意味かよくわかっていなかったけれど、フイルムで2倍撮れるってコトなんですね。勉強になりました。 |
|
|
|
| コメント作成 |
|
|
 0
0
|
|