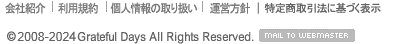https://maonline.jp/articles/why_are_funeralcompanies_going_bankrupt190521
江戸時代に創業した老舗葬儀社の桶孫(新潟県上越市)が2019年5月7日、新潟地方裁判所高田支部より破産手続の開始決定を受け倒産した。葬儀場「セレモニールーム大町」の運営や葬祭式典、霊柩運送、葬儀会員制度など葬儀ビジネス全般を展開してきたが、業績悪化に歯止めがかからず破産を選択した。
「価格破壊」でローカル葬儀社が次々と破綻
実は葬儀社の倒産は全国で相次いでいる。2018年8月に永盛葬儀社(東京都台東区)、同9月に愛永(相模原市南区)、同10月に聖雲会館(新潟県新発田市)、同12月にはコンノサービス企画(宮城県大崎市)と、ローカル葬儀社が軒並み経営破綻しているのだ。
厚生労働省の人口動態統計によると、2017年の死亡者数は134万人を超え、2000年と比べると約38万人も増えている。高齢化が進み死亡者数は増えるのだから、葬儀市場は拡大するはず。なのになぜ葬儀社の倒産が相次ぐのか?
最も大きな要因は葬儀の低価格化である。葬儀件数は増えても、葬儀「単価」が下落すれば売り上げは伸び悩む。その結果、この17年間で年間死亡者数が4割近く増えているにもかかわらず、葬儀社の経営が厳しくなっているのだ。葬儀「単価」が下落した背景には、二つの要因がある。
第一に葬儀の簡素化だ。かつては生前に親交のあった友人や近所の人たち、本人やその家族の職場仲間などが参列するのが当たり前だった葬儀も、最近では血縁関係の近い親族だけを招く「家族葬」が増え、故人の意思で葬式を行わない「直葬」すら珍しくなくなった。
帝国データバンクの「葬儀業者2163社の経営実態調査」によると、葬儀費用の平均は約200万円だが、首都圏の家族葬になると100万円以下と半額以下に下がる。特に墓地が高額な関東など都市部では、そのあおりを受けて直葬の比率が高まるという。
要は「葬儀にカネをかけるのか、それともお墓にカネをかけるのか」のせめぎ合いで、お墓を選ぶ人の方が多いということだ。最近は「終活」ブームで、故人が生前に葬儀や埋葬について決めるケースも増えた。「葬儀は遺族のメンツ、お墓は本人のメンツ」と言われるように、「葬儀よりもお墓にこだわる」トレンドになっているようだ。
葬儀業界は負のスパイラルから「レッド・オーシャン」に
第二に葬儀業界の競争激化である。「単価」が下落すれば、受注を増やすしか収益は上がらない。当然、葬儀の奪い合いとなり、低価格競争に突入する。そしてさらに「単価」が下落して、さらなる低価格競争に陥る…という「負のスパイラル」だ。
「価格.com」や「葬儀レビ」などの葬儀費用比較サイトのほか、葬儀社が自社サイトで「低価格」を謳(うた)い文句にするなど、主にインターネット上での低価格競争が葬儀「単価」の下落に拍車をかけている。
低価格競争が激化すれば、体力の弱い葬儀社から淘汰されていくことになる。同調査によると2017年度の年間売上高増加率は売上高100億円以上の大手葬儀社で前年比5.6%増なのに対し、1億円未満の零細葬儀社では同1.7%減と二極分化が進んでいる。実際、倒産しているのは地方の中小葬儀社がほとんどだ。
こうした厳しい環境はさらに続くとみられ、今後は大手葬儀社のシェア向上と中小葬儀社が生き残るためのM&Aが加速しそうだ。福島県を中心に葬祭事業や石材事業、婚礼事業を展開するこころネット<6060>は2017年12月に葬儀会社の玉橋(福島県本宮市)の全株式を取得して完全子会社化、2018年12月には冠婚葬祭事業を手がける北関東互助センター(宇都宮市)を完全子会社化している。
積極的なM&Aで急成長する葬儀社も現れた。葬儀社のM&Aによって、わずか3年で葬儀業界3位(同社推定)にまで駆け上がったライフアンドデザイン・グループ(東京都中央区)がそれ。もともと葬儀社を対象にしたコンサルタント業務を手がけていたが、その縁で2016年に洛王セレモニー(京都市南区)や神奈川こすもす(川崎市川崎区)を傘下に入れたのを皮切りに、ルミーナ(兵庫県丹波市)、セレサ(大阪市平野区)を相次いで買収した。
一方、流通大手のイオン
<8267>は子会社のイオンライフ(千葉市美浜区)を通じて「イオンのお葬式」で葬儀市場に参入しており、今後も異業種からの新規参入が加速するだろう。さらには大手葬儀社同士の
合併による「業界大再編」の可能性もある。今や葬儀業界は血で血を洗う「レッド・オーシャン」なのだ
今回は、葬儀屋さんを選ぶ時はどういう点に注意すべきななのか、とか、どうすれば費用を抑えることができるのか、といったことについての、最低限知っておいてほしい重要なノウハウを紹介したいと思います。
霊園や墓地が倒産!?大切なお墓はどうなってしまうのか?詳しく解説
https://ishinoya.co.jp/tomb/cemetery-bankruptcy/
会社や企業と同じように、霊園も倒産することがあります。
実際、2022年には北海道にある納骨堂が倒産しています。遺族には、事業の引き継ぎ先を検討すると説明したものの、約1ヵ月後には納骨堂が閉鎖されたというニュースは衝撃を残しました。
霊園や墓地が倒産する原因とは?
そもそも霊園や墓地を運営できるのは、限られた団体のみです。
なぜなら、霊園や墓地は恒久的・持続的な運営が必須であり、経営破たんがあってはならないと考えられているからです。それなのになぜ、霊園や墓地が倒産するのでしょうか?考えられる原因を探ってみましょう。
民間霊園の経営破たん
民間霊園とは、地方自治体が運営している霊園以外で、運営団体が宗教法人でない霊園を指します。つまり宗教法人でなくても、霊園を設立して運営できます。しかし霊園を経営する場合には、都道府県知事の許可が必要です。霊園経営の指針として、高い倫理性と組織や責任の体制が明確である点が求められます。そのため都道府県知事の許可を得るために、宗教法人から名義を借り、開発業者や石材店が運営しているケースもあるようです。このようなケースでは利益が追求されるため、経営の不安定さが霊園倒産の事態を招いています。
また墓地も人気・不人気があります。予想に反して利用者が増えず、資金繰りがうまくいかずに経営破たんに陥る場合があるようです。さらに、最近では永代供養が増え、お墓を建てない人も増えています。少子高齢化でお墓の承継が困難な家庭や、お墓の管理で子どもに負担をかけたくないと案じる方々が、墓じまいを検討しているのも霊園倒産の原因のひとつといえるでしょう。
寺院墓地の経営破たん
お寺の敷地内にある寺院墓地でも、経営破たんしたケースがあります。先述したように、少子高齢化で日本の人口が減るなか、檀家になる母数が減少しています。檀家が減ればお布施も比例して減少するため、寺院の経営自体が困難となっているのです。また檀家制度自体に疑問を感じる人も増え、檀家離れが加速しています。
こうした寺院の経営に不安を感じた住職が、民間企業からの営業に乗ってしまうのも無理はないでしょう。寺院墓地の倒産は、寺院が民間霊園の設立に名義貸しした結果、経営難に陥ったことが原因のひとつです。
倒産するとお墓はどうなるの?
霊園や墓地が倒産すると、今あるお墓や納骨堂はどうなってしまうのでしょうか。考えられるケースは、以下の2つです。
- 新しい法人が経営を引き継いで霊園を管理
- 遺族に遺骨の引き取りをお願いする
多くの場合、霊園や墓地の管理や運営を引き継いでもらえるよう、新たな運営団体を探しています。引き継ぎ先が見つかれば、お墓はそのまま維持できるでしょう。遺骨の取り出しや引越しの必要はありません。ただし、新たに契約を結び直すようになるため、永代使用料の請求や管理費の値上げを要求される可能性があります。
問題は、引き継ぎ先の運営団体が見つからない場合です。この場合、遺骨の引き取りを依頼されるでしょう。すぐに引き取りに行ければ良いのですが、対応が遅れると遺骨を引き取れない可能性があります。
また霊園や墓地を管理する団体が不在となるため、荒れ果てた霊園にお墓だけが残ってしまいます。納骨堂のように建物内で遺骨が管理されている場合は、お参りどころか遺骨の行方がわからなくなる可能性もあるでしょう。
お墓は強制撤去されるのか
じつは霊園や墓地が倒産しても、お墓は撤去されません。そもそも霊園や墓地を廃止する場合には、都道府県知事による墓地廃止許可が必要(墓埋法10条2項)です。また勝手にお墓を撤去しようと工事に踏み切ると、墳墓発掘罪などの刑法に触れる(第188条ないし第191条)可能性があります。
つまり、全ての使用者の許可と改葬が完了してからでないと、墓地経営は中断できません。遺骨の引き取りや墓石の撤去をお願いされたときに速やかに対応できなくても、お墓は守られます。ただし霊園の管理が行き届かないので、自費負担での補修が必要になる可能性があります。
霊園倒産によるトラブルを防ぐために
霊園倒産や墓地の経営破たんなどのトラブルに巻き込まれないために、次のような点に注意しましょう。
- どのような法人が経営しているか事前に確認
- 運営年数や契約数
- 安すぎる永代供養料や管理費に注意
- 派手な建物や過剰な広告
霊園や墓地で墓所を契約する際は、運営母体の確認が必須です。宗教法人が運営しているように見せかけて、民間団体が主体となっているケースもあります。ホームページやチラシ広告などをチェックし、どのような団体がどのような運営をしているか、ほかに展開している事業はないかを確認しておきましょう。その際、霊園を運営して何年くらいか、契約数は伸びているのかも調べておくと安心です。
また利用に関する費用も、運営状況を知る大切な情報です。永代供養料や年間管理費が、相場と比較して安すぎる場合は要注意しましょう。また、納骨堂や管理棟などがあまりに豪華だったり、テレビCMや新聞広告が過剰な場合も心配です。なぜなら一時的に資金を集めて、持ち逃げする可能性があるからです。
できれば複数の霊園を見学し、見積もりを取りましょう。比較検討すると、地域の相場がわかります。
霊園が倒産したときのお墓の引越し先
あってはならない事ですが、もしも霊園が倒産してしまったら、お墓の引越しを検討しましょう。管理の行き届かない霊園にお墓を残しておくと、お墓自体の劣化も進んでしまいます。ここでは、霊園が倒産した際のお墓のお引越し先として、考えられる改葬先を紹介します。
新しい霊園や墓地
もっともスタンダードな改葬先は、新しい霊園や墓地へのお引越しでしょう。遺骨のみを取り出して新たなお墓を建てるパターンと、墓石ごと引っ越すパターンの2つに分けられます。しかし墓石ごと引っ越すのは現実的ではありません。お墓を傷つけないように解体したり、運搬したりするのには、高額な費用がかかります。多くのケースで、新たに墓石を購入するのと変わらないほどの費用負担となるでしょう。また霊園によっては、指定の石材店で墓石を購入するように定められています。思い入れのある墓石であったとしても、諦めなくてはいけない可能性が高いでしょう。
合同墓・合祀墓
合同墓・合祀墓とは、家族以外の遺骨と一緒に埋葬されるお墓のことです。合同墓・合祀墓に改葬するメリットは、費用が安価で済む点でしょう。永代供養のお墓でもっとも費用がかからず、お一人当たり数万円~30万円程度で利用できます。草むしりや墓石清掃など、お墓の管理に手間がかからず、メンテナンスは全て任せられます。年間管理費も不要で、初期費用の負担のみで永代にわたって供養してもらえる点もメリットです。ただし、あとからお墓を新たに建てたいと思っても、一度合祀された遺骨は取り出せません。合同墓や合祀墓の利用は、慎重に検討しましょう。
樹木葬
樹木葬とは、桜や紅葉などの大きな樹をモニュメントとしたお墓のことです。ほとんどの樹木葬で永代供養が付いています。樹木の共有範囲はさまざまで、1家族で1本のタイプ、1本の樹木を複数人で共有するものの遺骨はそれぞれ分けるタイプ、他人の遺骨と混ぜ合わさってしまう合祀タイプなどがあります。共有範囲によって費用に差がありますが、合祀タイプは数万円で利用できるでしょう。1家族で1本のシンボルツリーを保有する場合は、50~150万円程度が相場といわれています。
納骨堂
納骨堂も、永代供養付きの改葬先として人気のタイプです。ロッカー型や位牌型、自動搬送型などさまざまなタイプがあります。アクセスしやすい場所にあるため、車の運転を控える年代になっても、公共交通機関で足を運べます。また建物内で管理されるため、お盆やお正月などの厳しい季節でも、快適にお墓参りできるようになるでしょう。納骨堂の費用相場は、10~150万円程度です。人数が少ない場合は、お墓を建てるより費用負担は少なくて済むでしょう。
問題は、納骨堂の維持費に運営側が耐えられるかどうかです。特に自動搬送型の納骨堂は、機械のメンテナンスにコストがかかります。想定よりも契約数が少なかったり、搬送の回数が多くコストがかかったりすると、運営を維持できない可能性があります。契約前には、納骨堂を管理している団体に、運営の見通しや修繕の予定などを確認しておきましょう。
手元供養
遺骨はお墓に納骨するもの、と認識している方も多いですが、じつはお墓に納骨する必要はありません。宗教的にも法的にも、お墓に納骨しなくてはいけないという教えやルールはないのです。引き取った遺骨を新しい骨壺に入れ、自宅で管理する手元供養も、改葬のひとつです。見た目の美しい骨壺に入れ、自宅で供養する方もいらっしゃいます。ただし手元供養は、一時的な対応でしかありません。供養している方が亡くなってしまえば、再度遺骨の行き先を探す必要があります。そのため手元供養として、いったん自宅に遺骨を持ち帰り、新しいお墓の形をゆっくり検討しても良いでしょう。
まとめ
霊園や墓地は、勝手に閉鎖されないよう法律で定められています。しかし、運営団体が経営破たんし、霊園や墓地が倒産する可能性は避けられません。
実際、霊園や墓地が倒産したトラブルはここ数年で急増しています。墓地や納骨堂を契約する際には、運営母体を調べておきましょう。運営年数や契約数、経営理念などの確認も必要です。少しでも不安を感じたり、疑問に思う点があれば、管理者への問い合わせをおすすめします。ご先祖さまの眠る「終の棲家」ですから、安心して遺骨を預けられる場所にお墓を建てましょう。