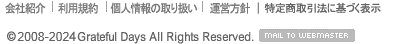高齢者の医療費は原則1割の自己負担だが、残りの費用は国や自治体の財源すなわち税金によってまかなわれている。医療費の保険給付金額は2025年には54兆円になると厚生労働省は試算しており、2018年よりも約10兆円以上増えると見込まれている。
言い換えれば、健康保険制度そのものの崩壊の危機につながる可能性もあるわけだが、こうした団塊世代の特異現象に対して政府はこれまでもさまざまな手を打ってきた。
たとえば、団塊世代が60歳を迎えて一斉に退職を開始してしまう、2007年問題に対しても、企業に定年退職の時期を60歳から65歳に延長するように求めた。政府が退職延長を打ちだしたことで、少なくとも2007年問題は「2012年問題」に置き換わることができ、大きな混乱を食い止めることができたと言われている。
一定以上の収入がある後期高齢者の窓口負担が増加
今回も、同様のことが考えられており、政府は今年10月から単身世帯で年収200万円以上、複数人世帯で年収合計320万円以上の後期高齢者は、医療費の窓口負担が現行の1割から2割に引き上げられることになっている。後期高齢者の約2割にあたる370万人がこの制度の適用になるが、施行後3年間は1カ月当たり最大3000円の負担になるように抑えられている。
団塊世代の当事者からすれば不公平感があるかもしれないが、65歳以上の高齢者が2040年には約4000万人に達するという「日本の将来推計人口」のシミュレーション(2017年の推計)を見ると、これもやむをえないはずだ。
医療費の負担も大きいが、75歳を超えて行くことで現実になるのが「介護問題」である。団塊世代を親に持つ世代にとっては、最も大きな問題になるかもしれない。
これまでの日本の介護システムは、ギリギリの状態が続いているものの何とかニーズに沿える行政サービスを提供してきたのではないか……。街の至るところに介護施設の建物があり、街中をヘルパーや搬送用の車が走っているのを見る機会が多くなり、介護への支援体制が整えられてきたことを実感できる。
しかし、現在でも自治体によっては、なかなか介護認定をしてもらえないケースが多く、要介護状態になっても介護施設に入れないと言う現実が待っている。今後は団塊世代が一斉に年齢を重ね、厚生労働省が発表している生命表を見てもわかるように、急速に老いて要介護状態になっていく。
ただ、団塊世代の特性として子どもには頼りたくない、と考えている人の割合が比較的、これまでの世代より高い傾向がある。内閣府が2012年に実施した「団塊世代の意識に関する調査」でも、「あなた自身が介護を必要になった場合、主に誰に介護を頼むつもりですか。また、頼んでいますか?」の問いに対して、次のような回答になっている。
「子どもには頼りたくない」という傾向が強い
●施設や病院等の職員・看護師等……18.7%
●ホームヘルパーや訪問看護師等……15.5%
●とくにいない……10.5%
●子ども……9.4%
要介護状態になっても子どもには負担をかけまいとする人の割合は約9割に達するわけだ。もっとも、有料老人ホームなどは少なくても月額20万~30万円超の経費が必要になっており、問題は年金給付金を頼りに生きている団塊世代が、金銭的に維持していけるかどうかだ。
退職金などの預貯金があるにしても、介護保険が出ている状況でも、大きな経済的負担になりやすい。ちなみに、介護保険制度を継続的に維持していくことを目指して、以前から年金受給者の介護保険料は年金給付金から直接天引きされる仕組みに変わっている。あらかじめ予定していた老後の資金計画に狂いが生じている人は少なくないはずだ。
いずれにしても、団塊世代が公的介護システムを頼りにできない状況になれば、その家族である子どもの世代=団塊ジュニアに頼るしかなくなる。
ちなみに介護保険というのは、65歳以上の「第1号被保険者」と45歳から64歳までの「第2号被保険者」で構成されており、要介護状態や要支援状態になれば保険金が給付されてさまざまなケアを受けられる仕組みだ。
2018年度末現在の数字では、第1号被保険者3525万人(65歳から74歳1730万人、75歳以上1796万人)、第2号被保険者は4192万人となっている。現在の要介護認定者数は、第1号被保険者では645万人、そのうち75歳以上は572万人に達している。
ちなみに、人口に対する要介護の認定率は75歳以上では32.2%(総務省統計局、人口推計および介護給付費等実態調査、2017年10月審査分)だが、85歳以上になると60.1%に上昇する。90-94歳では71.4%、95歳以上では92.8%に達する。年齢とともに確実に、要介護状態になるわけだ。
現在の団塊世代の収入の大半は、年金給付金に頼っていると言われる。年金給付金の具体的な金額は、厚生労働省「令和元年度(2018年)厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、平均年金受給額は年齢別に見ると次のようになっている。(厚生年金保険の平均年金月額、基礎年金額を含む。令和元年度現在。カッコ内は国民年金の場合)。
・72歳…… 14万5757円(5万6716円)
・71歳…… 14万6568円(5万6902円)
・70歳…… 14万7292円(5万6947円)
・69歳……14万2764円(5万6870円)
8割程度が年金で暮らしている
2012年に内閣府が行った前出の意識調査によると「団塊の世代の世帯の主な収入源」は次のようになっている。
・給与所得……31.6%
・事業や不動産の収入……10.2%
ちょうど団塊の世代が65歳にさしかかった頃の調査であり、まだ働ける人が多かった時期に当たる。おそらく現在では給与所得の31.6%は、その多くが年金所得に置き換わっているはずだ。つまり8割程度の人が年金をメインの収入として暮らしていると考えていいだろう。
団塊の世代の大学進学率は、当時約17%程度。そういう意味では平均的に見て決して豊かな年金給付金をもらっているとは言いがたいものがある。それでも、日本の場合は高度成長期を支えた団塊の世代に対して企業年金等手厚い福祉が充実しており、単純にこの年金額だけで団塊の世代の家計を判断してはいけない。
50兆円とも70兆円とも言われてきた団塊の世代の退職金の存在もある。そもそも団塊の世代の退職金が、使われずに銀行に滞留しているのも現在の日本経済の個人消費の伸び悩みと関係しているという説もある。その一方で、財務省の「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(2018年5月)」によると、年金などを含めた「社会保障給付費」を全体で見ると、2018年度の121兆円から2025年度には最大で140兆6000億円程度になると推計されている。自己負担分が増えていくのは目に見えているわけだ。
いずれにしても、現在の日本の公的年金制度が破綻せずに維持できるかどうかは正直わからない。新型コロナウイルスの影響で、日本銀行は相変わらず量的緩和政策やマイナス金利政策を維持しており、今後年金制度を維持させていくことができるのかどうかも含めて、将来は極めて不透明だ。世界的には、インフレが大きな悩みの種になろうとしているが、日本の場合、インフレになっても金利を上げることができない社会構造になっており、インフレには弱い社会基盤になっている。
年金受給者にとって、インフレは最も恐れる事態と言える。インフレが当たり前になったとき、団塊の世代もまたその混乱に巻き込まれることは確実だ。
団塊ジュニアの未来を気にして滞留する70兆円?
団塊世代にはもう1つ大きな問題が残っている。彼らの子ども、いわゆる団塊ジュニアの存在である。
1990年代の不況期に青春時代を過ごした彼らは、フリーターやニートといった形で社会人にならざるをえなかった「就職氷河期世代」とも重なる。雇用者の4人に1人は非正社員と言う状況の中で、「下流社会世代」という言葉までが流行語となった。さらには、自立できずに親に依存して生きる「パラサイト・ジェネレーション」とも言われた。
つまり団塊世代の中には、50歳前後になって、いまなお自立できない子どもたちを抱えている世帯が少なからずあるのではないか。「8050問題」とも言われており、団塊世代の退職一時金が団塊ジュニアの未来を危惧して銀行に眠ったままとなって、日本の個人消費の伸びを抑圧していると言う分析もある。団塊世代を親に持つ世代にとっては、自分の親たちが今後歳を重ねていくにしたがって、これからは自分たちの自立も考えなければいけない人が、ある一定数に上るのではないか。
そんな状況の中で、最近クローズアップされつつあるのが、団塊世代が亡くなった後のリスクだ。日本の持ち家比率から考えると、団塊世代の8割程度は持ち家を持っている勘定になるが、これがまた大きなリスクになっていくと考えられる。これが第4のリスク「団塊世代の相続問題」である。
幸いなことに団塊の世代の大半は、相対的に豊かな人が多い。月々の年金は大した事はなくても、前述のように彼らは豊富な貯蓄を持っていることが多い。加えて不動産を抱えている人が多い。実際に、団塊世代の持ち家率は86.2%(出所:内閣府、2012年現在、以下同)であり、そのうち一戸建ては75.3%、分譲マンション等の集合住宅が10.9%となっている。まさに大半の人が家を持っていると思っていいだろう。
相続税のほかにも維持費用がかかる
ところが、この不動産が団塊ジュニアにとっては大きな重荷になる可能性があると指摘されている。とりわけ都心部に不動産を持っている人は、まず相続税の問題があり、さらにそのまま相続して保有する段階になったときには「固定資産税」や「都市計画税」が重くのしかかり、大きな負担になる可能性が出てくる。
マンションであれば、「管理費」や「修繕積立金」が月額数万円の単位でランニングコストとしてかかってくる。不動産にはランニングコストがつきものであり、極端なケースで言えば、たとえば温泉付きの別荘を持っている親がいるとしよう。その場合には温泉の管理費やメンテナンス費用などもかかってくる。しかも、保有している限りついて回るコストだ。
地方の別荘地の物件が、10万円とか20万円の激安価格でよく売り出されているが、それらの大半は温泉の管理費用などで毎月一定のコストを負担しなければならず、保有しているだけで大きな負担になるために、処分を急いでいると考えるべき物件なのである。
最大で70兆円ともいわれる団塊世代の預貯金をそのまま遺産として残してもらえれば、不動産に少々コストがかかっても問題はないのかもしれない。しかし、団塊の世代も長寿であることに変わりはない。
人口統計からみれば、団塊世代の場合、男性の8割、女性の9割は現在も健在だが、その数字は80歳代では男性の6割、90歳では2割、95歳では5%になると予想される。それまで子どもに頼らずに有料老人ホームなどに入居していた場合、団塊世代の現預金は大きく目減りしている可能性が高い。
そもそも親の住んでいる不動産を相続したとしても、首都圏の平均的な住居の場合、敷地面積が200平方メートル以下の部分の住宅用宅地について適用される「小規模住宅用地の特例措置」がある。この特例措置があったとしても、固定資産税と都市計画税で年間15万円から20万円程度は覚悟しなければならない。この特例措置では、200平方メートル以下の部分は固定資産税が課税標準の6分の1、200平方メートル超の部分は同3分の1に、都市計画税もそれぞれ3分の1、3分の2に軽減されるのだが、これが適用されなければその金額はさらに大きなものになる。
空き家として放置しておけない
さらに大変なのは、空き家として放置しておくわけにいかないということだ。一戸建てであれば庭の雑草駆除や庭木の剪定をしなければならないし、ネズミなどの小動物が住み着いて近隣に迷惑をかけるような状態になれば、駆除費用などもかかる。むろん、メンテナンスもしなければならない。
マンションの場合も、住んでいなかったとしても、毎月数万円程度の管理費や修繕積立金は負担しなければならない。賃貸住宅として貸し出せばいいと考えているかもしれないが、人口減少の波はこれからさらに進んでいくことになり、簡単に賃貸住宅として埋まると考えるのは甘い。よほど立地のいいところでないとなかなか難しい。また賃貸に出そうとすれば、リフォームなどにお金がかかる。
社会は、住宅余剰の時代にさしかかっており、団塊世代が残してくれる財産は、ひょっとしたら団塊ジュニアの負担にしかならない場合もあることを忘れないことだ。
ちなみに相続放棄をすればいいと思うかもしれないが、相続放棄は不動産だけ放棄するというわけにはいかない。現金などの財産も一緒に相続放棄しなければならない。預貯金だけ相続して不動産は放棄するというわけにはいかないことを覚悟しておくことだ。
対策としては、生前贈与して賃貸物件化しやすいようにあらかじめリフォームしておく、あるいは亡くなる前に現金化してしまう方法などがある。不動産の専門家に相談しておくことだ。
団塊の世代は、これまでもさまざまな場面で新しいトレンドや時代の変革を演出してきた。いわば時代の転換点の主役となってきた部分がある。本格的な老後を迎えてきた団塊世代がさまざまな仕組みを大きく転換させてしまうきっかけになってしまうかもしれない。


























 (50)
(50)