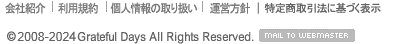https://the-owner.jp/archives/8971
2021年10月20日からマイナンバー保険証の本格運用が開始された。2022年4月17日時点で利用登録をした人は約830万人。マイナンバーカードと健康保険証が併用できる点にメリットを感じて保険証利用登録をした人もいるだろう。
日本政府は、マイナンバーカードのさらなる普及および健康保険証としての利用促進を目指してメリットをアピールしているが、デメリットも知っておきたい。
マイナンバー保険証のメリット
まずは、マイナンバー保険証のメリットを整理しておこう。これらは、日本政府がアピールしているマイナンバー保険証のメリットだ。
- 就職・転職・引っ越しをしても健康保険証としてずっと使える
- マイナポータルで特定健診情報、薬剤情報、医療費が見られる
- 窓口への書類の持参が不要
- マイナポータルで確定申告の医療費控除の手続きが簡単
参照:マイナポータル
例えば会社員の場合、健康保険証は会社で発行手続きをすることになる。そのため就職・転職をした際には、新たな就職先で健康保険証を発行してもらうことになる。また引っ越しや結婚して姓が変わったときには、住所や氏名の変更手続きが必要だ。しかし新しい健康保険証が届くのを待っている間に病気やケガで医療機関へ受診するケースもあるだろう。
そのような場合でも新しい健康保険証の発行を待たずにマイナンバー保険証で受診できるのは便利だ。救急などで医療費が高くなりそうなときにはなおさらだろう。医療費のつなぎでいえば公的医療保険に「高額療養費制度」がある。マイナンバー保険証で受診することでこの手続きの手間が省けるのもメリットといえる。
高額療養費制度とは、1ヵ月の医療費窓口負担が一定額を超える場合にその超えた部分が還付される仕組み。事前に申請しておけば医療機関の会計で多額の支払いをしなくてよくなる「限定額適用認定証」がもらえる。マイナンバー保険証で受診した場合、医療機関がシステム上で限定額適用認定資格を確認できるため、限定額適用認定証の提出も不要になるのだ。
マイナンバー保険証を利用すると処方された薬の情報などが履歴として残るため、診察をする医師も患者の同意を得たうえで履歴を確認しながらより適切な診察・処方が期待できる。これは、医師・患者の両者にとって安心につながるだろう。
マイナンバー保険証のデメリット
次に主なデメリットを3つ紹介する。
1.窓口負担が高くなる
「令和4年度診療報酬改定」により2022年4月1日からマイナンバー保険証で医療機関や薬局を利用した患者を対象に、医療費の窓口負担が上がった。公的医療保険の本人負担は医療費の3割と決められており、例えば本来かかる医療費が1万円なら本人負担は3,000円だ。
マイナンバー保険証を利用する場合、これにオンライン資格確認システム利用の対価として新たな料金が加算される。自己負担3割の場合、初診で21円、再診は12円。ただし受診の都度かかるわけではなく徴収されるのは、月1回となる。
マイナンバー保険証の活用により、上述したように過去の薬剤情報や特定健診情報を医師と患者で共有できる。しかし金銭的な負担が重くなることは、デメリットといわざるを得ない。
2.特定の医療機関でしか使えない
マイナンバー保険証は、医療機関や薬局がマイナンバーカードを読み取るためのオンライン資格確認システムを導入していなければ使えない。冒頭で記載したように2022年4月17日時点のマイナンバー保険証の利用登録者は約830万人。一方で同年同日のオンライン資格確認システム導入医療機関は、4万384件となっており希望しても実際には利用できない人も多くいそうだ。
3.紛失のリスクが高くなる
マイナンバー保険証は専用の読み取り機械(カードリーダー)で読み取る。「暗証番号」または「顔認証」を選択。顔認証を選択したものの顔認証がうまくいかない場合は暗証番号に切り替えることも可能だ。
健康医療情報を医療機関と簡単に共有できれば、もちろんメリットも大きい。ただ、持ち歩くことで紛失のリスクが怖いという人は一定数いるだろう。マイナンバーはこれまで家に置いていたという人も多いのではないだろうか。
持ち歩くことで紛失のリスクが高くなることは心にとめておいた方がいいだろう。
国がマイナンバー保険証を進めるワケ
なぜ日本政府は、マイナンバー保険証の活用を促進しているのだろうか。それは、マイナンバーと紐づけることで医療情報や保険料・納税額、口座情報などの個人情報を一元管理しやすくするためだ。近年は、超高齢化社会の進行とともに国の医療費負担も上がっており国の各種審議会で「負担能力に応じた負担を求める」ことも議論されている。
個人の金融資産や納税額、医療費等を把握して、医療費の自己負担を増やす意図も想像できるだろう。公平な負担は当然求められるべきものである。しかし現状のように「マイナンバー保険証を使うか」「通常の健康保険証を使うか」によって個人負担額が異なるようでは、公平とはいえない。
https://nukunukusas.com/my-number-card-as-health-insurance-card
- マイナンバーカードの健康保険証化のメリット7つ
- メリット①:「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請が不要になる!
- メリット②:マイナポータルで「特定健診情報」「薬剤情報」「医療費」の閲覧ができる
- メリット③:確定申告の「医療費控除」が自動入力できる
- メリット④:病院で健康保険証を持ち歩く必要がない(持ち歩くカードが1枚減る)
- メリット⑤:マイナンバーカードの更新や、電子証明書の更新を行っても、健康保険証の利用再登録は不要!
- メリット⑥:就職・転職・退職・引っ越ししても、協会けんぽなどに届出すれば継続で健康保険証として使える
- メリット⑦:利用開始申し込みは、オンライン資格確認に対応した医療機関や薬局でも可能
- マイナンバーカードの健康保険証化のデメリット3つ
- デメリット①:オンライン資格確認に対応した医療機関(病院や薬局)でしか使えない
- デメリット②:マイナンバーカード機能のスマホ搭載の対応時期が未定
- デメリット③:2022年4月1日から窓口負担が上がる(見直しを検討中)
- 現在は健康保険証を継続利用可能。2024年度以降は発行されない可能性あり!
- 5分でできる!マイナンバーカードの健康保険証利用の申込2ステップ
- マイナンバーカードの健康保険証化ステップ①:利用申込環境準備
- マイナンバーカードの健康保険証化ステップ②:マイナポータルから申込
- 医療機関で健康保険証化したマイナンバーカードの利用方法7ステップ
- ステップ①:医療機関に備え付けの「顔認証付きカードリーダー」に健康保険証化したマイナンバーカードをセット
- ステップ②:認証方法で「顔認証」か「暗証番号」を選択する
- ステップ③:顔認証か暗証番号で認証します
- ステップ④:【初回利用時】「薬剤情報・特定健診情報等の閲覧」に同意
- ステップ⑤:【利用未登録者のみ】マイナンバーカードの保険証利用登録
- ステップ⑥:「高額療養費制度(負担限度額認定)」を利用する場合
- ステップ⑦:受付完了!カードリーダーにセットしたマイナンバーカードを取り出します。
- 健康保険証化したマイナンバーカードを利用できる医療機関
- マイナンバーカードの健康保険証化のメリット7つとデメリット2つ まとめ
https://www.tokyo-np.co.jp/article/179885
厚生労働省は25日の部会で、「よりよい医療を受けるため」だとして、2年後には現在の健康保険証を廃止して、マイナンバーカードを保険証代わりにする方針を打ち出した。「国民皆保険」の日本だから、事実上、同カードの取得が義務化されるに等しい。これまでも政府はあの手この手で同カード普及を進めてきたが、医療を受けるという国民の重要な権利を人質にするような強引なやり方でいいのか。(特別報道部・木原育子、中沢佳子)
◆ポイントちらつかせて誘導しているだけ
26日正午、東京・御茶ノ水周辺。病床400床以上の大病院もひしめき、有名病院も多い地域だ。
駅周辺の広場で、無農薬野菜やドライフルーツの販売をしていた藤森孝幸さん(74)は保険証は外出時は必ず持ち歩く。「私たちのような年になると、いつ病院にかかるかわからないし」。保険証を廃止し、マイナンバーカードに一本化する議論が進んでいると伝えると、「えっ?なくなるの?」と驚き、「便利になるならいいけど、国の説明もいまいちよく分からない。マイナンバーカードも持っているが、言われるがまま持たされてるのが正直なところ」。
設備機器の営業をする途中で立ち寄った男性(51)は「次は保険証ですか…。露骨に外堀埋めてきた感じですね」とため息交じりに話す。「給付金を受け取る口座と連携したらマイナポイントをあげるとか、国民にポイントをちらつかせて誘導しているだけ。持ちたくない人の意見はいつもそっちのけだ」とし、「保険証ってかなり身近なもの。それがなくなるって結構大転換かと思いますが、急に降ってわいたような…」。
この保険証廃止方針が飛び出したのは厚生労働相の諮問機関で社会保障について話し合う審議会部会。25日、2024年度中に保険証を原則廃止し、保険証をマイナンバーカードに一体化させた「マイナ保険証」の利用を促す案が示された。将来的には運転免許証も統合され、一元管理化される見通しという。
◆保険証に運転免許証…一元管理怖い
仙台市から出張中の会社員山岡大祐さん(48)は「保険証も運転免許も資産も全て一元管理なんて、今の国のデジタル環境では、正直怖くてできない」とぴしゃり。「リスクは分散して管理しておきたい」と語る。
ベンチで昼休憩中だった歯科医師(36)は「良い面はある」とする。「例えば、血液をさらさらにする薬を飲んでいる患者さんに抜歯の手術をする場合は相当注意する。一元管理されることで、より適切な医療を提供できる」と話す。「医療現場は個人情報の扱いに相当気を使ってきた。一元化されると今以上に慎重さが求められる。ガイドラインを作るなど対策が必要だが、あまりに急過ぎる」
医学部受験を目指し予備校に通う男性(24)も「命に直結する話。なし崩しではなく、もっと議論しないと」と不安視する。大学在学中に脳出血を患い、生死をさまよった。奇跡的に助かった際、医療現場に魅せられ、医学の道を志した。「マイナンバーカードは利益をもたらす面もあるが、損失をもたらす危険もあるもろ刃の剣。国はリスクの面も語るべきだ」と話す。
◆保険証の議論は取得率100%に近付いた後の話
政府は本年度末までに、ほぼ全ての国民にマイナンバーカードが行き渡る目標を掲げるが、取得率は現在44%。経済ジャーナリストの荻原博子氏は「一般の人が保険証などとマイナンバーカードを分けておき、リスク分散しておきたい感覚はとても正常だ。マイナ保険証の議論は国民の合意が深まり、取得率も100%に近づいた後の話だ。リスクの説明はせず、良い話しか言わない国の姿勢は信用ならない」と話す。
健康保険証とマイナンバーカードを一体化して、国民にメリットがあるのか。